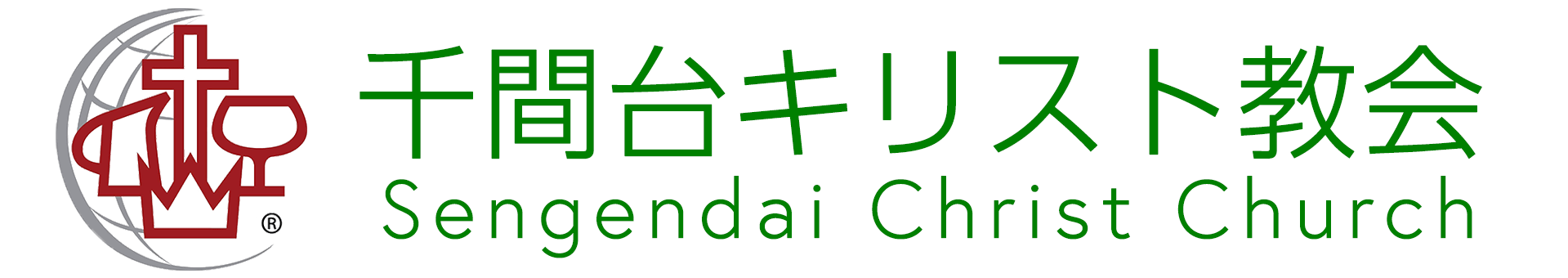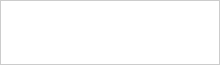年別アーカイブ: 2020年
誤解される中でも真実に… 2020.10.23
2020年10月23日 早天祈り会の御言葉
第Ⅱサムエル3:27-39 ヨアブはアブネルをひそかに呼び出し、殺します。理由は、ヨアブの弟アサエルをアブネルが殺したことに対する復讐でした。ダビデはアブネルが悪であることを知っていましたが、個人的な感情より …
高慢なアブネル 2020.10.21
2020年10月21日 早天祈り会の御言葉
第Ⅱサムエル3:1-16 サウルの家とダビデの家の間に長い戦いが続いていました。その間、アブネルがサウルの家で勢力を増していたことに注目する必要があります。それは、アブネルが戦いを利用してサウルの家すべてを飲み込もうとし …
傷のみ残る戦い 2020.10.20
2020年10月20日 早天祈り会の御言葉
第Ⅱサムエル2:12-32 サウルの息子イシュ・ボシェテの家来たちとアブネルはキブオンに来ました。一方、ヨアブとダビデの家来たちもキブオンに行きました。キブオンは、当時祭司たちの都市として一番重要だったので、アブネルはそ …
最後まで同じ心で 2020.10.19
2020年10月19日 早天祈り会の御言葉
第Ⅱサムエル2:1-11 ダビデがツィクラグにとどまっている時にサウルの死の知らせを聞きました。彼は悼み悲しんで泣き、哀歌を作って歌いました。それから、自分を殺そうとしていた人が死んだので、すぐに故郷に帰ることもできまし …
福音のために共に働く人たち 2020.10.16
2020年10月16日 早天祈り会の御言葉
コロサイ書4:6-18 使徒パウロは、安否を尋ねることで手紙を終えます。コロサイ書の中でも色んな人たちの名前が言及されています。そのすべての人が使徒パウロと共に働いた人たちの名前です。そして、その人たちの出生が皆違うこと …