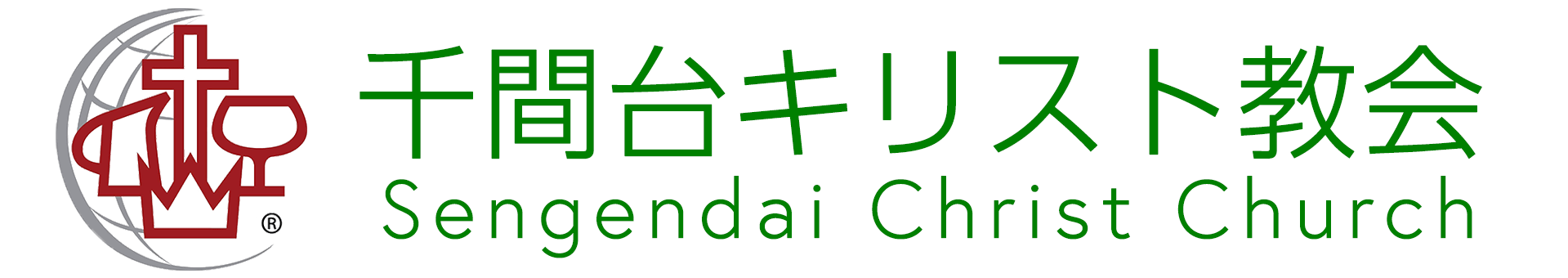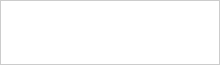年別アーカイブ: 2020年
何を大事にしていますか。 2020.08.29
2020年8月29日 早天祈り会の御言葉
Ⅰサムエル15:1-15 人は選択によって、何を心の中心にしているかが現れます。サウルの選択から現れた彼の本音は、何だったのでしょうか。神様がサウルに「言って、アマレクを討ち、そのすべてのものを聖絶しなさい(3節)」と命 …
主に祈る人生 2020.08.28
2020年8月28日 早天祈り会の御言葉
Ⅰサムエル14:36-52 サウルの性格はかなり衝動的であり、自己中心的であることが伺えます。民たちが肉を食べて気力を回復したのを見たからなのか、夜、ペリシテ人を追って行こうとします。戦争について神様に聞く姿はありません …
変化を起こさせる信仰 2020.08.26
2020年8月27日 早天祈り会の御言葉
Ⅰサムエル14:1~23 今日の箇所では、神様より人に寄り頼んでいたサウルと神様を信頼したヨナタンの姿が比較されます。サウルはペリシテ人たちを恐れ、600人の兵士たちと共にザクロの木の下に座っていました。「座っていた」と …
主を覚えよう 2020.08.24
2020年8月24日 早天祈り会の御言葉
Ⅰサムエル12:1~25 王を立て国を新しくする前の、サムエルの預言者としての最後の説教だと言えます。 サムエルは神様がイスラエルをどのように導かれたかを簡単に話しています。エジプトで導き出されたことから、士師を立てられ …
神様が立ててくださいます 2020.8.22
2020年8月22日 早天祈り会の御言葉
Ⅰサムエル11:1-15 サウルは神様から王として選ばれ、油注がれましたが、民たちまでがサウルを王として認めたわけではありません。サウルも自分を認めてくれないことについて何の不平もありませんでした。人たちに認められること …